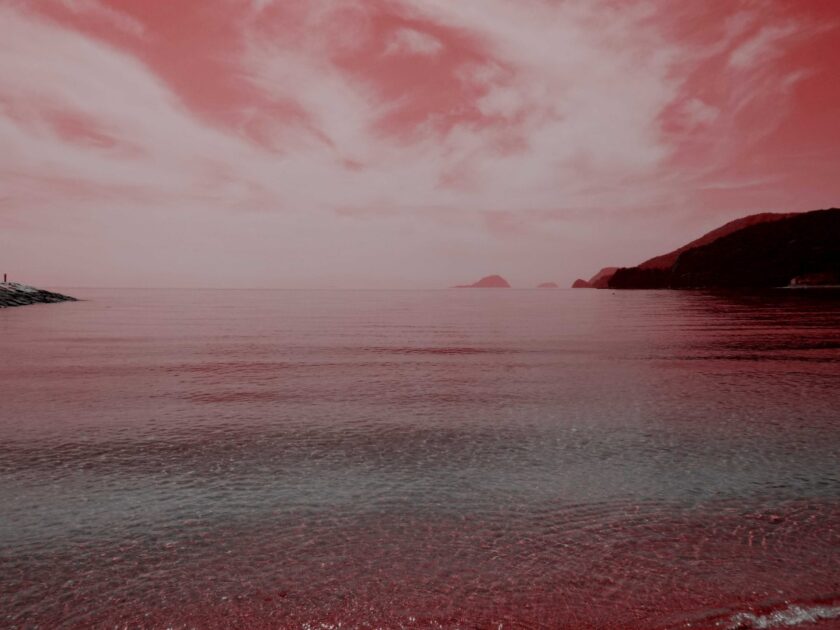Senryu-tei Syunsyo’s Novel Room(Novel-Ⅲ)
Evangelion SS「und der Cherub steht vor Gott!」
独房に蹲り、リツコは涙の滲んだ自分の膝をただ目に映していた。
不意に訪れた気配に闇を透かし見る。しかし闇の中には、誰もいない。
・・・誰も。・・・何も。
「やはり僕が下で寝るよ」
「いいよ、僕が無理言って泊めて貰ってるんだ。ここでいいよ」
与えられた部屋。およそ、ベッドと机と収納くらいしかなく、シンジが横になる場所を作れば文字どおりもう足の踏み場もない。
カヲルの言葉に、こんなに部屋が狭いとは思ってもみなかったらしいシンジが恐縮する。・・・・彼は作戦部長である葛城三佐と同居することで、郊外のマンションを住居として与えられているのだ。こんな場所が想像しにくかったのは無理もない。
しかしカヲル自身はこの場所に格段の感慨を持つことはなかった。・・・いずれ、カヲルの本当の居場所など、いまこの世界にはもう存在しないのだから。
「・・・君は何を話したいんだい?」
努めて直截に、カヲルは言った。シンジが薄闇の中で、言葉を選びかねて口を僅かに動かすのがわかる。
「・・・僕に聞いて欲しいことがあるんだろう?」
ここまで言わねばならないものかとも思う。だが結局、迂遠なもの言いは彼を惑わせるだけのようだ。
―――――彼が本当に心を開いて、話をしてくれるまで待ってあげられたら良かったが・・・。
暫時の間があり、シンジは訥々と話し始めた。
「いろいろあったんだ・・・ここに来て。来る前は先生のところにいたんだ。穏やかで、何もない日々だった。ただ、そこにいるだけの。・・・でもそれでも良かったんだ。僕には何もすることがなかったから。生きることに、僕は何もなかったから」
多分、自分は昔の夢を見たがっているのだ、とカヲルは思う。
エデンの記憶を除いて、唯一彼が大事にしてきた記憶。・・・畏怖でなく、嫌悪でなく、そして好奇でもないまなざしを与えてくれた、ただひとりの・・・。
カヲルを生き延びさせようと、心を砕いてくれた同胞たち。その犠牲の上に今日を築きながら、ひとり優しい夢を見ようとする自分は、愚かだろうか。
「人間が嫌いなのかい?」
なかば自分の記憶に語りかけるように、カヲルは問うた。
「別に・・・どうでもよかったんだと思う。・・・・・・・ただ、父さんは嫌いだった」
後半のフレーズに含まれた、敵意と背中合わせの思慕。それに彼は気づいているのだろうか。カヲルは首をめぐらせて、天井を見つめているシンジを見た。
不意に、シンジがこちらを見て、目があったことに少しびっくりしたような顔をする。視線をあわせて話すことが苦手なのだろう。・・・・カヲルは、彼が視線を反らせてしまう前に言った。
「僕は君に逢うために・・・生まれてきたのかもしれない」
人工進化研究所第3分室。
塗料の剥げかけた扉には、そういうプレートがついている。
綾波レイはその扉を開け、内部の暗闇に憶することもなく入ると、無造作に片手を伸ばした。
闇の中で、スイッチが彼女の手に触れる。次の瞬間、暗闇は眩しいほどの光にとってかわられた。
―――――現れたのは、ひどく寒々しい室内。
継ぎ目が腐食し、あるいは剥げかけたリノリウムの間から、コンクリートの床が覗く。中央にベッドがひとつ、白い衝立がひとつ。ベッドの周囲はいかめしい器械が取り囲み、さらにその周囲の床は太いコードが何本も、さながら古い蛇のようにのたうっていた。
それらすべてがひどく時代がたったものと見えるのに、消毒剤の匂いだけが妙に鮮明であった。
しかしレイは、そういった寒々しさになんら関心をむけるでなく、ベッドに歩み寄ると腰かけた。・・・何をするわけでもない。ただ、床頭台の上に転がる割れたビーカーが、場違いなほど強い照明をはねているのを漫然と見つめていた。
不意に、身体を硬くして立ち上がる。
「誰?」
今レイが入ってきた扉の反対側は、続き部屋への入口になっていた。無論そちらには照明がついておらず、そこはさながら部屋の一隅がぽっかりと黒い口を開けているかのように見える。
その暗闇の奥に誰かがいる。
「誰?」
もう一度問う。ややあって、足音がその人物を連れてきた。
「・・・・・・?」
出てきた人物を見て、レイは――ひどく珍しい事ではあるが――困惑していた。
「・・・ごめん、驚かせるつもりはなかったんだけど。君とは思わなくて」
困惑している自分に苛立ちを覚えてか、レイの声はやや鋭角的だった。
「・・・なぜここにいるの」
レイの問に、カヲルは少し考えるようにあらぬ方を見やる。
「・・・ここは立入禁止区画よ」
「そういう君は、なぜここに来たんだい?」
「ここは私の生まれた場所だもの」
レイの返答は、余人であれば目を剥いたであろうものであった。それにもかかわらず、彼は静かだった。ただ、「そう」と短く答えたのみ。
「・・・・ここにいたんだね」
そう呟いた彼の表情は、レイの理解を越えるものであった。
「・・・・・あなたが何を言っているのか分からないわ。ここで何をしているの」
「調べ物さ」
「何を」
「さぁ?」
韜晦するがごとき笑みに、レイは反応しなかった。
「・・・・・あなた、誰?」
昼間と同じ問を、彼女は繰り返した。
彼女を、自分と同じだと言ったこの少年から、レイは確かに何かを感じていた。その「何か」の正体がつかめないことに対して苛立っていたのだと、彼女は知った。
「いずれ分かるよ。君は君の思う径を行けばいいんだ。君は人形じゃないんだから・・・・・」
そう言って微笑んだカヲルの、先刻とは違う・・・涙さえ浮かべているのではないかと思うような双眸を見て、レイは苛立ちが沸点に達するのを感じた。
しかしレイは、それ以上何も言わなかった。・・・言えなかった。
だからただ、身を翻して足早にそこを立ち去った。
遠ざかる足音を聞きながら、カヲルはその場に立ち尽くしていた。
不意にカヲルの後ろで、廃棄されたモニタの灰色の画面が、低い唸りを発して黒く変わる。
最初に現れたのは、意味のない記号や英文字の羅列。
現れた文字列は瞬く間にモニタを埋め尽くし、スクロールされモニタの上端に呑み込まれていく。
カヲルは、ゆっくりと振り返った。
意味のない記号や文字は残らず消え去り、真っ黒な画面の中央に、一言だけ。
『・・・・・・・・・泣いているのかい?』
モニタに浮かび上がった言葉は、そのままカヲルの頭にも響いた。あるいは、カヲルが感じ取ったのか。
「・・・・泣いてなんかいない。涙なんて、もう僕には残っちゃいないさ」
その言葉通り、カヲルは泣いてなどいなかった。しかし、いっそ泣いてしまったほうが楽になるのではないかと思えるほど、苦しげな表情であった。
――――――――だが、苦しさを振り切るように閉ざした瞼をあげたとき、カヲルの口許には穏やかな笑みがあった。
「・・・やはり、生きていたんだな。あなたも」
カヲルの頭の中に響く声にも、モニターに浮かび上がる文字が現れるまでにも、僅かな間があった。
『・・・彼とは事情が異なる。生命の定義からは逸脱した存在かも知れないよ、今の僕はね』
「それでもいい、生きているなら」
表情とは裏腹に、その声音は年齢不相応なほど枯れていた。
「あなたは 運命から自由になった。生きていればどうにでもなる。・・・・生きていれば」
『・・・君もそうだよ』
カヲルは首を横に振った。
「僕は繋がれている」
『断ち切ればいい。君にはその力がある』
「ないよ、そんなもの」
『アルミサエルは君に言わなかったかい?・・・・僕らのためにする選択ならば、それはやめてほしいって』
カヲルは沈黙した。モニターの発する低い唸りだけが、部屋を満たす。
「僕はあなたたちが考えてるような者じゃない」
『何者である必要もないさ。・・・君は君であればいいんだ』
暖かな言葉は、かえって残酷だった。モニターから目を逸らすように、カヲルが俯く。
そして紡がれたのは、暖かさを振り払うような、硬い声。
「・・・あとひとつだけ・・・どうしても確かめておきたいことがあるんだ。それまでは老人達の掌で踊ってやるさ」
モニターから目を逸らしても、声は直接伝わってくる。
『手伝えることはあるかい?』
「あなたも、皆もひとりで戦った。僕もひとりでやる」
『・・・君ひとりが犠牲になってすべてを良しとする結末なんか、僕は納得しないよ』
カヲルは紅瞳を伏せていたが、ややあって決然と顔をあげ、言った。
「・・・・・・いずれ、明日には幕が上がる」
何故、彼を思い出したのだろう?
闇の中で、彼女を訪った気配に、彼女はある人物を思い出していた。
死亡が確認されたわけではないが、おそらくはもういないであろう人物を。
彼が恐怖と呼ばれる第11使徒であったことを、確たる証拠もないというのに、リツコは確信していた。
だが、確信したからといってどうなるものでもない。彼は死んだ。
彼女が殺した。
憎しみもないのに。
何故殺した? ―――――――使徒だから。
他にどうしようもなかったから。
MAGIを見殺しにできなかったから。
碇ゲンドウの信を失うことが出来なかったから・・・・・。
だが今彼女は、ダミーシステム破壊の簾で任を解かれ、こうして独房にある。
所詮ゲンドウにとって彼女はMAGIをシステムアップし、EVAを開発するための技術者でしかなかった。
・・・・もっと端的に言えば、母の代わりだ。
誰も彼女を見てなど、いなかったのだ。
誰も・・・・・・・
「・・・・よくここが分かったわね」
ぼんやりとした照明が点灯したときも、リツコは顔をあげなかった。
「聞きたいことがあるの」
「ここでの会話、録音されるわよ」
「構わないわ。 ・・・・渚 カヲル・・・あの少年、フィフスの正体は何?」
前置きも状況説明もない問いは、リツコがそれを知っているという前提のもとに投げかけられている。
だがそれが、母から引き継いだ、碇指令にすら知らされない部分を含んでいることを・・・彼女は知って問うているのだろうか?
ゼーレがネルフを、正確には碇指令の独走を制御するために隠し持っていたジョーカー。セカンドインパクト後の南極で散逸したもののうち、完全な姿でゼーレの手の内に残ったただ一つの「極秘サンプル」。
それに母がかかわっていたのは、母も自身が利用される存在であることを気づいていたからかもしれない。
人間の遺伝子を用い、人間に酷似した容姿をとらせた使徒。破滅を導く者。
ゼーレが送り込んだ「フィフスチルドレン」。他の何者であろうはずもない。
硝子管の中から、優しいだけに深い断絶を感じさせる笑みでリツコを見た・・・かの、裁きの天使。
リツコは、ゆっくりと言葉を紡いだ。
「・・・・おそらくは、最後のシ者」