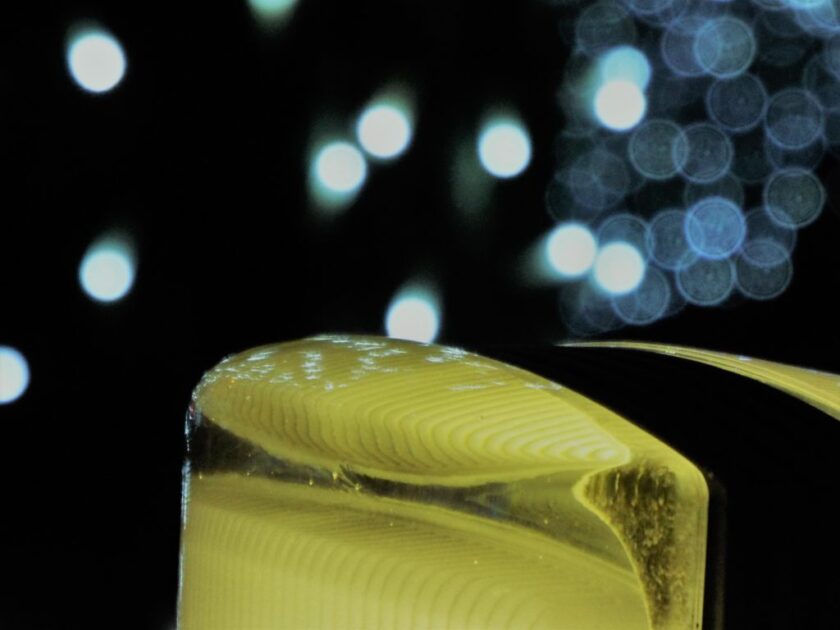「この時間じゃ、家でユカリが何か用意してたとしても粗方喰い尽くされた後だな。…何か食べて帰るか」
トレッキングコースの入口に停めた車まで戻って、マサキが腕時計を見遣った。
カヲルは長時間の強行軍にさすがに疲労していた。結局、丸一日山歩きに費やした格好なのだから無理もないのだが、マサキが全く平気な風なのが何か口惜しい。何か食べに出るというより、このまま少し脚を休めたいというのが本音ではある。
だが、それよりも。
「…予測していた?碇ゲンドウが、1st-cellとの不適合で余命があまりないことを?」
途中の猫の話といい、病人を連れ帰るというより遺留品の回収に向いた準備といい…そうとしか思えない。
「可能性としてはあり得ると思っていたな」
手にしたタブレットで近辺の店舗情報を物色しながら、あっさりとマサキは認めた。
「存外健脚に動き回るから、あるいは逃亡っていうケースも考えなくはなかった。
実直に、回復したところで社会的には抹殺されたに等しい。ユイ博士が責任能力なしとして追及を振り切ってるからのんびり療養生活だったにしても、『碇ゲンドウ』は二度と表には出られない身の上には違いないからな。
…まあ、畢竟、逃亡といえば逃亡なんだろう。全てからのな。
あのまま院内で管理されてれば相応の寿命はあったのかも知れないが、無茶苦茶な山中行で1st-cellの生命維持にかかるポテンシャルを消費い切った…ってのが妥当なところじゃないかな」
「逃げるって…ユイ博士からも…?あんなに懸命なのに…」
「あのおっさんには過ぎた女房だと俺は思うね。こればかりは外側からはかれることじゃないから、あのおっさんの何がよかったんだかさっぱりだが」
マサキはタブレットを閉じて言った。
「…お前どうせ、もう一歩も歩きたくないだろう。途中で何か買ってやるからそのまま休んでろ」
「悪いけど、研究室の方へ回してくれる?」
「まだ仕事するつもりですか?ちゃんと休んでくださいよ」
「まさか。忘れ物を取りに行くだけよ。すぐ出てくるから、待ってて」
どのみち大学の研究棟はリツコのマンションからそれほど離れているわけではないから、然程道順が変わりはしない。
研究棟のすぐ脇に車を停めた。言葉通り、リツコは5分ほどで出てくる。然程大きな物でもなかったのか、その手にあるのは車を降りたときと同じクラッチバックがひとつ。
「ありがとう。ごめんなさいね、この距離なら私、歩いて帰ったってよかったんだわ」
「今更でしょ。乗ってください」
「それもそうね。それじゃ、お言葉に甘えるわ」
助手席に滑り込み、リツコがドアを閉める。シートベルトを締め終わるのを見てから、タカミがエンジンを始動させた。
「今日はありがとう。またあなたたちに助けてもらったわ」
「結果として僕は何もできてませんけど」
「庇ってくれたじゃない」
「えーと…」
タカミが天を仰ぐ。
本来、タカヒロが床を切り取り、リエの転移によってタカミが降り立つ事で、床を下に落とす算段だったのだ。それが、タカミの体重がわずかに足りなかったようで落下が止まってしまった。イサナが機転を利かせてくれた(…というかおそらく予測していた)お陰でそのラグは最低限で済んだが、そうでなかったらと思うと今でも寒気がする。
一歩間違えればリツコに怪我をさせるところだった。その上、自分が依頼しておきながら、あの瞬間だけミサトのことをきれいに失念していたのだ。奇跡的に物理防御には成功したようだが、そうでなければあの距離であの数の銃口に狙われたら、自分の身一つで二人は到底庇いきれなかった。
「どっちかっていうと…僕は謝らなきゃならないんですが。いろいろと」
「あら、どうして?」
「今回はたくさんご迷惑かけましたし」
「それについてはもう解決したことだし、あまり気にしないでくれるほうが私としては助かるわ。まあそれに、榊くんがこのまま留年だの中退だのって話になっちゃったら、これからのプロジェクトに関わってもらいにくくなるじゃない」
『ご迷惑』の中身を微妙にすり替えられた気はしていたが、タカミは既に別のことに注意を惹かれてしまっていた。注意深く、問い返す。
「…また、行ってもいいんですか?研究室」
「もう来ないつもりだったの?」
涼やかな微笑とともに少し意地悪く問われて、思わずステアリングに置いた手に額をつけてしまう。危うくクラクションを鳴らしてしまうところだった。
「えーと…行っていいものならまた行きたいな…と」
「じゃあ、よろしくね。どうせ、会議室での会話は途中から聞いてたんでしょ?旧ドイツ支部の評価としては、私と一緒に引き抜いてもいいくらいの『優秀なブレーン』らしいじゃない。他所へ連れてかれちゃかなわないわ。
…ああ勿論、冬月先生の手前もあることだから、とりあえず無事に卒業して頂戴ね」
「肝に銘じます」
自分の顔色がどうなっているかと思うと、顔を上げるに上げられなくて…タカミはステアリングに額を預けたままそう言った。
「サキは食べないの」
テイクアウトのクラブサンドとコーヒーを片付けて、包装紙を折り畳みながらカヲルは言った。マサキは自身の分も買ってはいたが、クラブサンドに手はつけず、ドリンクホルダーに置いたコーヒーを信号停止の間に啜るだけだ。
「車を停めて食ってる間があったら、さっさと帰って寝たい」
「…一応疲れてるんだ」
何も自分だけがへばっていた訳ではなかったのかと、カヲルは少しほっとした。
「そこそこな。どっちかっていうと、碇博士への説明を考えていたら食欲が失せたんだが。まあ、そのままを伝えるしかないか…」
そう言って、苦い顔をする。結局、疲労の色の原因は山歩きより碇博士のほうらしい。
「…ひとつ、訊いていい?」
無意味な敗北感に静かに落ち込みそうになり、カヲルは話を変えた。昨年末あたりから気になっていたが…なんとなく機会を逸したり、巧妙に逸らされたりして、訊き損ねていた。
「…サキは、タカミが赤木博士と関わりを持つことに反対なの?」
マサキが一瞬だけ間を置いてから、小さく吐息した。
「引っかかるな、お前も」
ドリンクホルダーからコーヒーを取ると、一口含む。信号停止でもないのに手をつけたところを見ると、逸らされていたと思ったのは思い過ごしでもなかったようだ。
「出会ってしまったものは仕方ない、なるようにしかならん…って、イサナには言ったつもりだったがな。何を聞いたか知らんが、どうせあの辺からだろう?」
コーヒーを置く。
「…『I’ll be by your side,always and forever…』」
その言葉の意味は分かっても、脈絡が掴めなくて…カヲルはマサキを見た。だが、そこにはいつもの晦ますような笑いはなく、ただ深い寂寥だけがあった。
「高階博士を看取ったあと、高階夫人が俺達に遺した言葉だ」
「ブリジット・オーレリア・サーキス=高階…」
「当時もう、彼女だって余命幾許も無い状態だったんだがな。彼女もそれを解っていた。それでも、彼女は笑っていた」
「いつも、いつまでも…」
「無理なんだよ。…高階博士も夫人もリリンで、俺達はネフィリムだ。どうしたっていつか時間っていう絶対の壁に分かたれる。…それでも…」
そこで、一度言葉を切った。
「…まあ、額面通りじゃなくて…俺達があの二人のことを忘れない以上、あの二人はいつも俺達と一緒にいるってことなんだとは思う。前にも言ったが、特に高階博士は科学者というより…多分に神父寄りな性格の御仁だったからな。彼女もまあ、おっとりした夫君に補いをつけるみたいにシビアな現実感覚の持ち主ではあったが、性格としては概ね似たようなものだったし。
…ああ、なんだか話が逸れた気がするな。
あのまま、もう出会うことがなかったなら…思い切れたんなら、そのほうがあいつにとっては幸いだったんじゃないかって話さ。
でも、出会ってしまったんなら仕方ないだろう。なるようにしかならんよ。
半世紀越しの片恋に理詰めの物言いをつけるほど、俺は野暮じゃないつもりだぞ。ただ、タカミはネフィリムで、赤木博士はリリンだ。こればかりはどうしようもない。ここからコトがどう転ぶにしたって、最後に泣くことになるのはどっちか、明白だろう」
そこまで言って、マサキはもういちどコーヒーを手にしかけ…それが空になっていることに気づくと、細く吐息して手を離す。
「…時が訪れたとき、またタカミが壊れるところなんて見たくない…って?」
運転中だからか故意か、マサキの視線は前方を見たまま動かない。
応えが返るまでにそれほどの時間を要したわけではない。ただ、声は何かをその裡で抑え付けるような低い響きを持っていた。
「そうだな、正直…二度と御免だな」
当時アベルと呼ばれていた少年の、苦しみから隔離するためには眠らせておくしかなかったという酷い状態を、今のタカミから推しはかることは難しい。しかしマサキの反応を見る限り、彼らが初めて「同胞を喪う」という危機を認識するほどに危険な状態まで陥ったのは確かなようだ。
それでも彼は帰ってきたのだ。…見つけることが出来たから。
カヲルはヘッドレストに頭を預けて、マサキと同じ景色をその紅瞳に映した。街灯のオレンジがかった光が何度かダッシュボードを洗って行くのを見送ってから、ゆっくりと口を開く。
「…イサナが、サキのことを根っから苦労性って言ってたの…理解った気がするな」
「肝を焼かせる奴らの面倒見てばっかりいると、自然とそうなる。…ん?根っからだと?俺は後天性だと思ってるぞ。あれだって言えた義理か。
ところでカヲル、何を笑ってる」
「いや、別に…」
そう言いながら、カヲルはこみ上げる笑いを堪えるために先刻折り畳んだ包装紙を力一杯握り締めなければならなかった。
「サキ、タカミはきっと、あなたが思ってるほど…弱くはないよ?」
リツコのマンションの前に整備されている来客用の駐車場には、今は他に駐めている車もなかった。
エントランス近くの区画にCX-3を滑り込ませて、タカミはエンジンを切った。駐車場に等間隔で設置されたガーデンライトが、前照灯の光が消えても車内に曖昧な光を投げかけている。
リツコが、膝の上に置いていたクラッチバックから掌に納まる程の小さな包みを出した。
「今日はありがとう。遅くなってしまったけど…これはあなたに。…下戸だって言ってたけど、このくらいは大丈夫よね?」
「えっ…あ、はい、多分…あ、ありがとうございます」
包装紙には誰でも知っているスイーツブランドの名前が印字されている。質の良い洋酒を使っていることで有名だ。「掛け値なしの下戸」と白状したあとのことで多少ばつが悪いのか、見ていて面白い程うろたえながら…タカミがそれを受け取った。リツコが微笑む。
タカミは少しの間だけ、視線を手の中の包みに落としていた。ややあってそれを胸ポケットにしまう動作の間に、ふいとその表情が翳る。
「苦手っていっても、アレルギーって訳じゃないんでしょ?」
茶化すつもりで言ったのだが、存外深刻そうなので一瞬心配になる。だが、自分の表情に気づいたのか、すぐにその翳りをはらって言った。
「あ、いえ、それは大丈夫」
笑みさえ浮かべてみせたが、それが「みせた」だけなのがありありと判る。
「…僕はね、リツコさん。他にもあなたに内緒にしてたことがあるんです」
ステアリングに置いた自身の手を凝視めながら、タカミはゆっくりと…区切るように言った。
「僕があなたに会ったのは…あなたが怪我してサキのところに運び込まれた時が最初だって言いましたけど…ごめんなさい、あれ…嘘です。
僕は、ずっと前からあなたを識ってました。…あなたが生まれるずっと前から。
僕らが、あなた方が使徒と呼んだ存在と、現生人類の融合体って話はもうご存じですよね。みんな、できることはそれぞれ違うんだけど…僕はすこし特殊な感覚を持ってるんです。
時間と空間を越えた認識…本来は、僕ら自身が何者であるかを認識するためのものらしいんですけど、僕は至ってコントロールが悪くて…こことは少しズレた時間軸の、しかも遠い未来を見てしまった。
…もう、半世紀ぐらい前のことです」
少し蒼褪めて、俯いたままの言葉を…リツコは静かに聞いていた。そういう者だとは聞かされてはいたものの、今まで巧く繋がらなかったことを改めて口にされると、やはり戸惑いを禁じ得ない。
「そこではとても怖ろしいことや、悲しいことが、たくさん起こって…僕なんかには勿論、誰にもどうしようもなくて…たくさんの人が非道い理由で死んで…殺されていったんです。
…リツコさん、あなたもです」
それを口にするために、彼は凄まじいエネルギーを要したのだろう。自身の胸を片手で押さえつけながら、絞り出すような声であった。しかし、リツコは実のところそれほど衝撃を受けることもなかった。この世界にしたところで、一つ間違えればそうなっていた。…彼らに出会うことがなければ。
「どうしたらそれを回避できるのか…僕は狂ったみたいに観測を繰り返しました。すこしでもましな未来があるのなら、そっちへ近づけたいと思って。…でも駄目だった。多分、観測を繰り返すうちにちょっとずつ基準にとる時間軸もずれていったんだと思う…どんどん酷いことになっていって…結局、僕は一度壊れてしまったらしいです。
らしい、っていうのは、僕にその時の記憶がほとんどないからなんですが。みんなに、物凄い迷惑をかけたみたいです」
一度、深く息を吐つく。
「永い間、眠ってたらしいです。そして眼を覚ましたとき、ようやく逢えたあなたはやっぱり泣いてて…僕は凄く悲しかった。
あなたには、笑ってて欲しいのに。
でもまだ、僕が見た未来とは違ってたんです。だから、まだ何かできると思った。…まあ、実際僕に何かできたかっていうと…何もできなかったんだけど。あなたを助けたのは結局…葛城さんやサキだったし。
だから、あなたが研究の手伝いに誘ってくれた時…僕はとても嬉しかったんです。あなたが、とてもいい顔で笑ってたから。
あなたがいつでも、あの時みたいにいい顔で笑っててくれるなら…僕は何だってします。僕にできることなんてそれほど多くないんだけど…多分、僕はそうするために此処へ戻ってきたから。
僕はCODE: Nephilimと呼称される者です。だから、いつまで此処に居られるのかも、実のところ判らない。サキが言うように…今は一応協力関係にあるヴィレだって、ある日突然ゼーレのような、ネルフのような組織に変貌することも可能性としてはないわけじゃない。それでも、僕は此処に居たいと思う。
…あなたが好きだから。 笑ってるあなたの傍に居たいんです。勿論、あなたがそれを許してくれればだけれど」
そこまで言って、ようやくタカミが顔を上げた。言うべきことを言い終えたというような、穏やかな笑みがそこにある。ガーデンライトの淡い光は、薄闇の中で柔らかな翠を浮かび上がらせた。静かだが、確かな熱を持ったその翠。
昨日のことだ。研修棟の前での、偶然の出会い。リツコが回り道の理由を口にした時、この翠が見る見るうちに翳り、端正といっていい造作が青褪めていくのを見た。
…ああ、知っているんだ。そう思った時には遅いのだが、特段に後悔に類するような感情は生まれてこなかった。もう過ぎたことだったから。ただ、リツコにとってはそうでも…目の前の青年にはそうではなかったのだ。
考えてみれば当たり前なのだ。かつて彼と、彼の家族に…あの男がいったい何をしたか。たとえ現在、社会的に抹殺されたも同様な身の上であったとしても、到底赦せるものではないだろう。…かつてそのごく近くに居た者も、また。
それでも、来てくれた。リツコ自身、今回の話にきな臭さを感じていなかったわけではない。だが、研究を続けるためにはどんなチャンスも逃せないから、敢えて回避しなかった。結果、危うく拉致されかかったが、彼らのお陰で事無きを得た。イサナという青年は碇博士の依頼と言っていたが、本来あまり荒事向きとは思えない彼が、敢えて最前線へ飛び込んできたことには正直驚いた。
この想いに、自分は応えることができるだろうか。
こんなふうに求められたことはなかった。碇ゲンドウは結局、自身の目的のために必要だったから接近してきただけ。そして、母を亡くして拠り所を喪っていた自分が、それを拒みきれなかったのが現実。研究の方向性について行けない、ついてこないことが判ってしまうと、いとも簡単に捨てられた。
何を莫迦なことをやっていたのだろうと、今になって思う。
あの時求められたのは自分ではない。科学者としての赤木リツコだ。それも、赤木ナオコの技術と知識の継承者である赤木リツコ。…つまりは母の影。
…科学者としての母は今でも尊敬している。しかし、女としては憎んでさえいた。今思えば、呆れるほどに意味のないことではあったが。
「…ありがとう」
…ふと、これで答えを返したことになるのだろうかと不安を感じる。我知らず伏せていた眼をあげたとき、少し落ち着かなげな緑瞳と視線が絡みあって、リツコは自分の不安が的中したことを知った。
小さく吐息する。全く、言葉というものは難しい。
「『読む』のはマナー違反と思ってる…のよね、あなたは。まあ、それは確かに正しいコトなんだけど…時と場合ってものがあるでしょうに」
「…えーと…リツコさん?」
この問題の解は判っているのに、方程式が提示できない。だから、ひょっとして自分は狡いのかも知れない…と思いながら、リツコは目の前…少し緊張しさえしている顔の、癖のある栗色の髪が被った額に指先で触れる。
自身の頬の熱さを自覚しながら。
「これで伝わる?それとも…私は全部言わなきゃならないのかしら?」
置かれた指先に掌を重ねて、一瞬戸惑うように翠色が揺れる。だが、それもふわりと凪いだ。
「…じゃ、あなたに触れてもいい?」
今度は、彼は答えを待たなかった。いつもの柔らかな笑みを浮かべ、タカミは重ねた手を握ってそっとリツコを引き寄せた。
「…Always and forever, I’ll be by your side..」